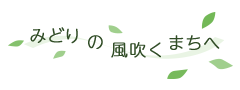食中毒に注意しましょう!~8月は食品衛生月間です~
- トップページ
- 保健・福祉
- 衛生
- 食品に関すること
- 食品に関するその他のお知らせ
- 食中毒に注意しましょう!~8月は食品衛生月間です~
ページ番号:148-880-337
更新日:2025年8月1日
暑くなるこの時期、心配なのが食中毒です。食中毒予防の三原則を守って、食中毒にならないよう十分ご注意ください。
食中毒予防の三原則
細菌・ウイルスをつけない
- 外出から帰った時、トイレの後、調理する前、食事の前などには、必ず手を洗いましょう。
- 調理に使用する器具類は、十分に洗浄・消毒したものを使い、生の肉や魚に使用したものを使い回さないようにしましょう。
- 牛、豚、鶏などの生肉には食中毒菌が付いていることがよくあります。生肉をさわった後は手や、使った器具をよく洗いましょう。
- 焼肉をする時は、生肉を取る箸と、食べる箸を使い分けましょう。生肉にさわった箸で食べてはいけません。トングの使用をおすすめします。
細菌を増やさない
- 調理前の食材や調理後の食品は、室温に放置しないようにしましょう。
- 食べるまでに時間がかかる場合には、ラップをして冷蔵庫にしまっておきましょう。
- 冷蔵庫は10℃以下に、冷凍庫は-15℃以下に保つように温度管理をしましょう。
細菌・ウイルスをやっつける
- 肉や魚などを調理する場合は、中心部までしっかり加熱しましょう。
- 再加熱する時も、しっかり加熱しましょう。温める程度では不十分です。
- 肉や魚などの生ものを扱った調理器具等は、よく洗った後、熱湯などを使って消毒しましょう。
![]() ねりま食品衛生だより第65号「気になる食中毒と予防の基本」(PDF:150KB)
ねりま食品衛生だより第65号「気になる食中毒と予防の基本」(PDF:150KB)
![]() ねりま食品衛生だより第66号「キレイに洗浄!正しく消毒!」(PDF:141KB)
ねりま食品衛生だより第66号「キレイに洗浄!正しく消毒!」(PDF:141KB)
食中毒予防の第一歩は手洗いです
手を洗うタイミングは?
- 料理、食事の前
- 生ものをさわったあと
- 外から帰った時
- トイレのあと
![]() ねりま食品衛生だより第70号「しっかり手洗いで予防しよう!」(PDF:541KB)
ねりま食品衛生だより第70号「しっかり手洗いで予防しよう!」(PDF:541KB)
営業者の方へ
調理した食品を長時間暑いところに保管したり、冷たい食品と温かい食品を一緒に詰め合わせると、食中毒を発生させるおそれがあります。
お客様へ提供する料理は、特に以下のことに留意して調理しましょう。
製造に際しての注意事項
- 製造能力を超えた注文を受けない。
- 冷蔵庫内を常に整理し、庫内での食材・料理の相互汚染を防ぐ。
- 使用する調理器具は、洗浄消毒したものを使い、使い回しをしない。
- 食材・料理の提供までの時間を短くし、前日調理をしない。
- 冷たいものは冷たく、温かい物は温かいうちに提供する。弁当などに一緒に詰め合わせない。
提供する際の注意事項
料理は、出来上がったものをすぐに提供するのが基本です。
しかし、仕出し弁当など、製造から食べるまでの時間が長くなる可能性のあるものは以下の点に注意してください。
- 配送には保冷剤や保冷ケースを使い、料理の温度が上がらないようにする。
- なるべく食べる予定の時刻直前に配達する。
- 配達先で保管場所、時間などの注意喚起を忘れずに行う。
持ち帰り(テイクアウト)や宅配(出前)を始める飲食店の皆様へ![]()
ご家庭では
家庭内での食中毒を予防するために、特に以下の事柄に注意しましょう。
冷蔵庫の使い方
- 冷蔵庫は詰め込みすぎると、冷えにくい部分ができて菌が繁殖してしまいます。
- 空気の通り道を確保して、冷気が循環してよく冷えるよう、庫内の整理を心がけましょう。
- 適宜、庫内を掃除しましょう。
行楽時のお弁当
お弁当を作る時は次の点に注意しましょう。
- 前日から作り置きをしない。
- おかず(から揚げ、ハンバーグ、卵料理など)は、十分に加熱し、生焼け・半熟にならないようにしましょう。
- おかずはよく冷ましてから詰め合わせましょう。
- おにぎりはラップなどを使って握り、直接手に触れないように作りましょう。
- 車の中や直射日光の当たる場所など、温度が上がりやすい場所に置かないようにしましょう。
ねりま食品衛生だより第74号「食中毒に気を付けよう お弁当やおうちごはん」![]()
水筒、やかんなど金属製の容器の使い方にご注意
水筒ややかんなどの金属製の容器を使って、スポーツ飲料や炭酸飲料、乳酸菌飲料、果汁飲料など酸性の飲料を作ったり入れたりすると、容器の金属成分が飲み物の中に溶け出して中毒を起こすことがあります。次の点にご注意ください。
- 食品が接触する容器の内部に、サビや傷がないかよく確認しましょう。
- 酸性度の高い飲み物や食べ物を、金属製の容器に長時間保管しないようにしましょう。
- 古くなった容器は、定期的に新しいものに交換しましょう。
- 取り扱う食品や容器の表示や、注意事項を確認してから使用しましょう。
テイクアウト等を利用する時には
食中毒の予防には時間と温度の管理が重要です。テイクアウト等は、店内で食べる時と比べて、調理してから食べるまでの時間が長くなります。特に次の点に注意しましょう。
- 食品を購入したらすぐに帰宅し、長時間持ち歩かないようにしましょう。
- 早めに食べましょう。すぐに食べない場合は、冷蔵庫で保存する等、長時間常温で放置しないようにしましょう。
- 再加熱する時は中心までしっかり加熱しましょう。
- 食べる前にはしっかり手を洗いましょう。
テイクアウト等を利用するときのポイント(消費者庁)(外部サイト)![]()
肉の生食、生焼けに注意しましょう
肉を生で食べるのはやめましょう
とりわさ、鶏刺しなどの生肉料理や、焼肉などで加熱不足の肉やレバーなどを原因とする食中毒が頻発しています。食中毒の原因菌としては、カンピロバクター(外部サイト)![]() によるものが多くなっています。生肉や生の内臓類を刺身やタタキなど生で食べたり、生焼けなどきちんと火の通っていない物を食べるのは非常に危険です。肉を生で食べるのはやめましょう。
によるものが多くなっています。生肉や生の内臓類を刺身やタタキなど生で食べたり、生焼けなどきちんと火の通っていない物を食べるのは非常に危険です。肉を生で食べるのはやめましょう。
肉の生食による食中毒予防のポイント
- 肉は生で食べると、食中毒になることがあります
肉の生食等による食中毒の原因菌であるカンピロバクターや腸管出血性大腸菌(外部サイト)![]() は、少量の菌で食中毒を起こします。新鮮であっても、菌が付いている肉を生で食べれば、食中毒になる可能性があります。
は、少量の菌で食中毒を起こします。新鮮であっても、菌が付いている肉を生で食べれば、食中毒になる可能性があります。
- 子供や高齢者が肉を生で食べると、特に危険です
カンピロバクターによる腸炎は、子供に多く発生します。子供に限らず、カンピロバクターによる食中毒の後、手足のまひ、呼吸困難等を起こすギラン・バレー症候群を発症することがあります。また、腸管出血性大腸菌による食中毒では、合併症で溶血性尿毒症症候群(HUS)を発症する率が子供において高く、腎機能障害や意識障害を起こし、死に至ることがあります。
- 「生食用」の牛レバー、豚肉は流通していません!
牛レバーの内部には、鮮度や衛生管理の方法にかかわらず、腸管出血性大腸菌がいることがあります。また、豚肉は、E型肝炎ウイルス(外部サイト)![]() 、食中毒菌、寄生虫に汚染されているおそれがあります。そのため、現在、牛レバー、豚肉(内臓を含む。)を生食用として販売・提供することは法律で禁止されています。
、食中毒菌、寄生虫に汚染されているおそれがあります。そのため、現在、牛レバー、豚肉(内臓を含む。)を生食用として販売・提供することは法律で禁止されています。
鶏肉には生食用の衛生基準がありませんので、生で食べると食中毒になる可能性があります。
牛レバーを生食するのは、やめましょう(厚生労働省)(外部サイト)![]()
豚のお肉や内臓を生食するのは、やめましょう(厚生労働省)(外部サイト)![]()
肉の低温調理は正しく加熱
近年流行している肉の「低温調理」は、中心部まで加熱が不十分になりがちです。生の食肉は、食中毒の原因となる菌が付着していることがあるため、特に注意が必要です。
低温調理機器の設定温度まで水温が上がっても、食材の中心温度が上がるまでに通常の加熱調理に比べ時間を要します。
低温調理した肉の見た目だけでは、食中毒を防ぐ安全な加熱をできたかどうか判断するのはほぼ不可能といわれています。
低温調理をする際は、低温調理器各メーカーが出している公式のレシピ等に従い、適切に温度と時間の管理をしましょう。
肉を低温で安全においしく調理するコツをお教えします!(内閣府 食品安全委員会)(外部サイト)![]()
ジビエ(野生鳥獣の肉)はよく加熱して食べましょう
ジビエとは、シカ、イノシシなど狩猟の対象で、食用になる野生の鳥獣や、その肉のことです。
生または加熱不十分な野生のシカ肉やイノシシ肉を食べると、E型肝炎や腸管出血性大腸菌症の食中毒のリスクがあるほか、寄生虫(外部サイト)![]() の感染も知られています。ジビエは中心部まで火が通るようしっかり加熱して食べましょう。
の感染も知られています。ジビエは中心部まで火が通るようしっかり加熱して食べましょう。
また、接触した器具の消毒など、取扱いには十分に注意してください。
ジビエ(野生鳥獣の肉)はよく加熱して食べましょう(厚生労働省)(外部サイト)![]()
その他の食中毒
上記以外にも食中毒の原因には様々です。以下のリンクも参考にしてください。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
![]() Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
健康部 生活衛生課 食品衛生担当係
組織詳細へ
電話:03-5984-4675(直通)
ファクス:03-5984-1211
この担当課にメールを送る
このページを見ている人はこんなページも見ています
法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202