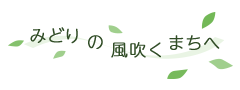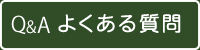2 生き生きとした長寿社会の実現
- トップページ
- 区政情報
- 計画・報告・方針など
- 練馬区長期総合計画(平成13年度~22年度)
- 練馬区長期総合計画
- 事業計画 第1章 だれもが健やかで生き生きと暮らすために
- 2 生き生きとした長寿社会の実現
ページ番号:477-020-292
更新日:2010年2月1日
現状と今後の動向
練馬区における平成12年(2000年)4月現在の高齢化率は14.9%で、10年後の平成22年(2010年)には20.5%になると予想されています。現在、高齢者人口に占める要援護高齢者の割合は12%で、今後、高齢化の進展に伴って、要援護高齢者の増加が見込まれています。また、ひとりぐらし高齢者や高齢者のみの世帯も年々増加しています。
平成12年度から介護保険制度が実施され、介護サービスは保険制度を中心に進められることになりました。この制度では、介護サービスの内容を利用者自身が選択し、サービス提供事業者と直接契約するという新しい考え方が導入されています。さらに、国において、社会福祉基礎構造改革が進められており、これまでの行政がサービスの内容を決定する措置制度から、利用者が自らサービスを選択して利用する制度へと大きく仕組みが変わります。このため、今後は利用者が選択するために必要なサービスの質・量を確保することが求められていきます。
高齢者をめぐる今後の状況の変化に対応していくためには、高齢者のサービス利用や生活実態の把握に努め、次のような視点に立つ施策の展開が必要です。
(1)都市化の進展や地域社会の人間関係の希薄化等に伴って、高齢者の価値観やライフスタイルは多様化しています。このような中で、高齢者一人ひとりの個性や経験が生かせるよう、社会参加や生きがい活動を支援していくとともに健康な高齢者の活躍できる機会の創出が必要です。さらに、地域社会で高齢者を支える活動への支援やそのネットワークづくりを進め、高齢者が地域社会の中で生き生きとして暮らせる環境を整備していく必要があります。
(2)高齢者の多くは、住みなれた地域で安心して、家族や親しい隣人に囲まれて暮らしていくことを望んでいます。健康づくりや介護予防策の充実を図るとともに、介護が必要な高齢者でも、身近なところで援助が受けられるように、在宅支援サービスのメニューを充実させていくことが一層重要になります。
(3)高齢者が地域社会の一員として、住民相互の支え合いの中で生活していけるよう、地域の福祉施設や人的資源の有効活用を図り、地域社会における連携・協働を進め、ネットワーク化を図ることが必要になります。
(4)高齢者がそれぞれの身体状況や家庭状況に応じて、適切なサービスを受けられるように、サービス内容の向上を図り、十分なサービスの量を確保する必要があります。 また、保健・医療・福祉施策の一体的・総合的なサービス供給体制の整備を進めていくことが必要です。
(5)明るく活力に満ちた高齢社会をつくるためには、高齢者が自らの経験と知識を生かして、他世代の人々とも交流しつつ、積極的な役割を果していけるような場と機会づくりが必要です。
施策の方向
(1)生きがいづくりと社会参加の促進
(1)学習・スポーツの機会の充実
高齢者が個性を生かし、意欲的な活動ができるよう、生涯を通して参加できる学習・スポーツの機会の充実を図ります。
(2)世代間交流の促進
高齢者の生きがい増進のために、高齢者が長年積み重ねた知識や経験を若い世代に伝えるとともに、他世代との相互理解を深めるための世代間交流事業を、老人クラブや敬老館、児童館、学校等に働きかけ促進します。
(3)老人クラブの育成
高齢者が、老人クラブに参加する等地域社会に積極的に参加し、生き生きと健康で生きがい活動や健康づくりに取り組めるよう、老人クラブや老人クラブ連合会の育成、支援を行います。
(4)就労相談の充実
高齢者の生活の安定と向上を図るとともに生きがい対策のために就労相談を充実します。
(5)シルバーボランティア活動の促進
高齢社会における高齢者間の支え合い等のボランティア活動の調整機能の充実と支援体制の充実を図り、シルバーボランティア活動を推進します。
(6)シルバー人材センターへの援助
働く意欲をもつ高齢者の経験と能力を生かす場のひとつであるシルバー人材センターの充実を図るため、支援を行います。
(2)健康の保持増進と介護予防
(1)介護予防施策の充実
閉じこもりや寝たきりになることを予防するため、生きがいづくりや健康の保持増進のための事業を保健・医療・福祉の連携のもとに実施していきます。
(2)高齢者保健事業の充実
高齢者の健康の保持増進を図るために、健康診査、健康教育、健康相談を充実するとともに、食生活支援のため、講習会の場と機会の充実を図ります。
(3)リハビリテーション体制の充実
虚弱高齢者等を対象に、身近な場所でレクリェーションやスポーツ等の活動を通して、ADL(日常生活動作)の維持向上や生活障害の改善を図り、あわせて社会参加を促す地域参加型リハビリテーションを実施します。
(4)健康管理の充実
高齢者の健康管理を充実するために、関係機関と連携し、健診後の事後指導の充実を図ります。
(3)在宅支援サービスの充実
(1)在宅支援サービスの整備
高齢者が、介護が必要な状況となっても、住みなれた地域社会の中で安心して自立した日常生活を営むことができるよう、訪問介護(ホームヘルプサービス)や通所介護(デイサービス)などの介護保険サービスの充実を図るとともに、生活支援に必要な在宅サービスを提供していきます。
(2)ひとりぐらし高齢者等食事サービスの充実
ひとりぐらし高齢者や高齢者のみ世帯で食事サービスを必要とする方に定期的に食事を提供し、地域社会との交流および安否確認、健康の保持を図ります。
なお、その際、閉じこもりや寝たきりになることを予防するため、会食型食事サービスを推進します。
(3)地域ケア体制の確立
保健・医療・福祉の各サービスを一体的に提供するため、訪問援護チームによるサービスの調整や相談機能の充実を図ります。
また、地域におけるケア体制を確立するため基幹型や地域型の在宅介護支援センターを整備するとともに、地域ケア会議を活用して訪問援護チームや介護サービス機関、ボランティアなどが連携して、サービスの調整と供給の支援を図ります。
(4)地域支え合いネットワークの構築
ひとりぐらし高齢者や高齢者のみの世帯等が安心して暮らせるよう、住民参加による地域支え合いネットワーク体制を構築します。
(5)痴ほう性高齢者への総合的な施策の構築
痴ほう性高齢者と家族の負担の軽減化を図るために、介護保険制度との整合性を図りながら、専門医による早期相談体制や保健婦(士)等による訪問指導や相談体制を整備し、痴ほうの予防・早期発見を図るとともに、サービス提供により悪化の防止を図ります。
さらに、痴ほう性高齢者の権利を擁護し、自己決定が尊重されるよう施策の整備を図ります。
(4)高齢者福祉サービス基盤の整備
(1)地域高齢者センターの整備
健康の増進、教養の向上およびレクリエーションのためのサービスを総合的に提供するため、地域高齢者センターを整備します。
高齢者間のコミュニティづくりを進める施設として、機能の充実を図るとともに、敬老館等の高齢者施設の事業に対する支援機能を持たせます。
(2)要援護高齢者実態調査の実施
高齢者の保健・医療・福祉サービスの利用や生活実態を把握し、要援護状態の方の在宅サービス施策に反映できるように調査研究を行います。
(3)高齢者福祉施設の整備
特別養護老人ホームやデイサービスセンター、短期入所施設、痴ほう性高齢者グループホーム、在宅介護支援センター等の整備を社会福祉法人や医療法人、NPO等に働きかけるとともに必要な支援を行います。また、小中学校の余裕教室等既存施設の有効活用を検討します。
(4)介護老人保健施設の整備
病状安定期にあり、入院治療の必要がない寝たきり高齢者等の家庭復帰を支援する拠点として、医療法人等の介護老人保健施設の整備を支援します。
(5)介護療養型医療施設の整備
長期療養に適した環境を必要とする要介護高齢者のために、介護力強化病院の療養型病床への転換等、介護療養型医療施設の整備を国や都および関係機関に要請します。
(6)敬老館の改修
エレベーターの設置、段差の解消等、高齢者が利用しやすい施設とするため、併設の児童館等の改築計画と一体的に、敬老間の改築を検討します。
(7)情報提供体制の整備
サービスを必要とする区民の保健・医療・福祉に関する情報を一体的に提供できる体制を整え、申請やサービス利用に役立てることができるように情報提供体制を整備します。
また、だれにもわかりやすい情報提供に努めます。
(8)相談機能の充実
身近な在宅介護支援センターでの高齢者相談機能の一層の充実を図るとともに、総合福祉事務所を中心にした高齢者の相談体制を整備します。
(9)保健・福祉の人材確保・育成
介護能力をもつ福祉人材を広く確保するため、民間の介護人材確保・育成を支援していきます。また、区民のボランティア活動への参加意欲に応えるため、社会福祉協議会と連携し、ボランティア人材の確保を進めます。必要に応じて人材育成の研修等を実施します。
(5)生活基盤の整備
(1)高齢者集合住宅等の整備
住宅に困窮するひとりぐらし高齢者や高齢者のみの世帯が住みなれた地域で暮らし続けられるような新たな住宅供給支援策として、良質な居室を借り上げて提供します。
また、都営住宅の立て替えに当たり、高齢者集合住宅(シルバーピア)の確保を要請します。
さらに、高齢者向け優良賃貸住宅の供給の支援を検討します。
(2)公的年金・手当、医療費助成、貸付制度の充実
老後の経済生活の根幹をなす公的年金・手当をはじめ、医療費助成、各種貸付金制度の充実について国、都に要請します。
(3)特別養護老人ホーム経過措置対象者の対応策
特別養護老人ホーム経過措置対象者の退所後の生活の場として、高齢者集合住宅(シルバーピア)やケアハウス、養護老人ホームでの受入れや、自立生活支援策を検討します。
施策の体系
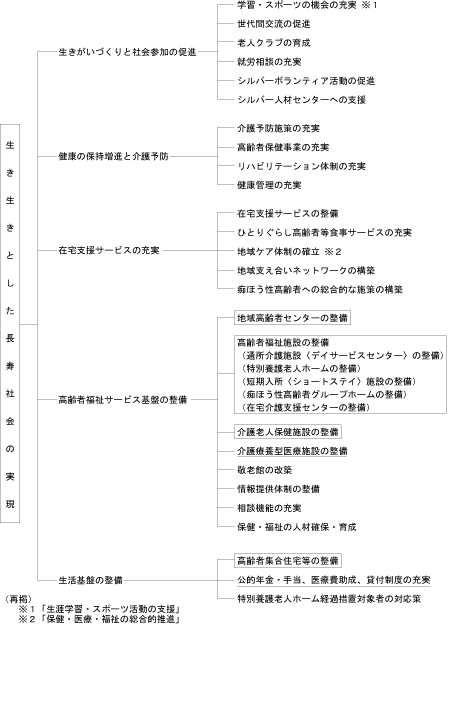
計画事業
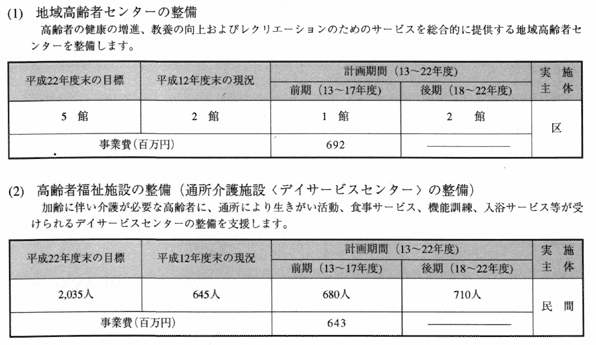
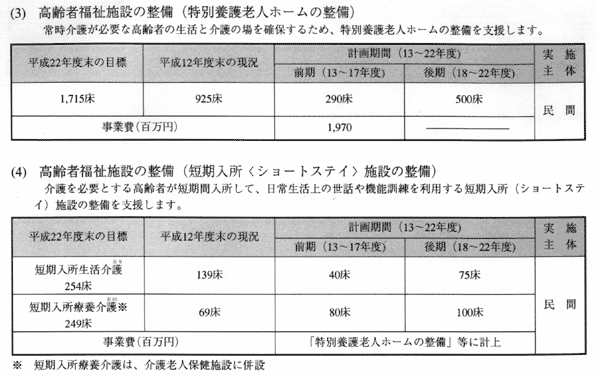
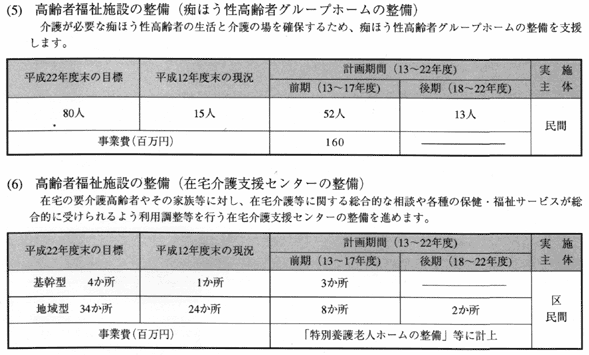
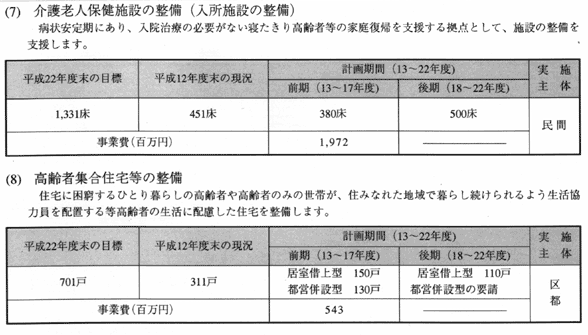
お問い合わせ
企画部 企画課
組織詳細へ
電話:03-3993-1111(代表)
この担当課にメールを送る(新しいウィンドウを開きます)![]()
このページを見ている人はこんなページも見ています
法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202