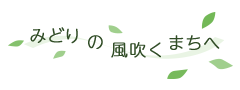均等割額の減額(国保)
- トップページ
- くらし・手続き
- 国保・後期高齢者医療・年金
- 国民健康保険
- 国民健康保険の保険料
- 均等割額の減額(国保)
ページ番号:904-477-233
更新日:2025年4月1日
未就学児の均等割額の減額
世帯内の未就学児(6歳に達する日以後の最初の3月31日を迎えていない方)で、国保に加入している方の均等割額を5割減額します。
対象者は自動的に減額になります。申請は必要ありません。
※下記の「前年所得による均等割額の減額」が適用される世帯に未就学児がいる場合、その方の当該減額後の均等割額をさらに5割減額します。
前年所得による均等割額の減額
世帯の所得が一定基準以下の場合、基礎(医療)分・後期高齢者支援金分・介護分保険料の均等割額が減額になる制度があります。減額割合は7割・5割・2割のいずれかです。
下記「減額基準表」に該当する世帯は、自動的に減額になります。申請は必要ありません。
なお、この減額の適用は、税の申告内容に基づき判定されるため、世帯主(国保に加入していない世帯主を含む)、加入者および旧国保加入者(※1)のうち一人でも税の申告をしていない方がいる場合は、減額判定の対象となりません。
所得がなかった方は税務署で行う確定申告は不要ですが、住民税の申告をおすすめします。
期限より遅れて税の申告をしたことなどにより減額が適用となったときは、年間保険料を再計算し、減額適用の決定された月以降に納める保険料で調整して通知します。
減額基準表
【一定の給与所得者等※2が1人または0人の世帯】と【一定の給与所得者等※2が2人以上いる世帯】で減額基準表が異なります。
均等割額の |
世帯主(国保に加入していない世帯主を含む)、国保加入者および |
|---|---|
| 7割減額 | 43万円 以下 |
| 5割減額 | 43万円 + 30.5万円×国保加入者および旧国保加入者数※4 以下 |
| 2割減額 | 43万円 + 56万円×国保加入者および旧国保加入者数※4 以下 |
均等割額の |
世帯主(国保に加入していない世帯主を含む)、国保加入者および |
|---|---|
| 7割減額 | 43万円 + 10万円×(一定の給与所得者等※2の数 -1) 以下 |
| 5割減額 | 43万円 + 30.5万円×国保加入者および旧国保加入者数※4 |
| 2割減額 | 43万円 + 56万円×国保加入者および旧国保加入者数※4 |
※1 旧国保加入者とは、後期高齢者医療制度に移行(加入)するために国民健康保険を脱退してからも、引き続き国保に加入している方と同じ世帯にいる方です。
※2 一定の給与所得者等とは、世帯主(国保に加入していない世帯主を含む)、国保加入者および旧国保加入者※1のうち、給与収入が55万円を超える方または、公的年金等の収入が60万円(昭和35年1月1日以前生まれの方は125万円)を超える方です。
※3 減額基準表に使用する所得は国民健康保険料の算定に使用する「旧ただし書き所得」とは異なります。下記の点にご注意ください。
- 国保に加入していない世帯主の所得も含みます。
- 住民税基礎控除は控除しません。
- 65歳以上の方(昭和35年1月1日以前生まれの方)で公的年金所得がある場合、公的年金所得から15万円を控除します。
- 事業主が計上している専従者控除は事業主の所得として算定します。専従者が受け取る専従者給与は専従者の所得としません。
- 長期譲渡所得・短期譲渡所得に係る特別控除はないものとします。
- 雑損失の繰越控除がある場合は、控除後の金額になります。
※4 国保に加入していない世帯主は含みません。
お問い合わせ
区民部 国保年金課 こくほ資格係
組織詳細へ
電話:03-5984-4554(コールセンター直通)
ファクス:03-3993-3260
この担当課にメールを送る![]()
このページを見ている人はこんなページも見ています
法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202