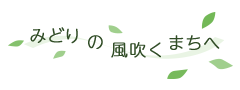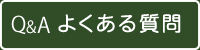総論1. 21世紀初頭の新たな潮流
- トップページ
- 区政情報
- 計画・報告・方針など
- 練馬区長期総合計画(平成13年度~22年度)
- 練馬区長期総合計画
- 総論1. 21世紀初頭の新たな潮流
ページ番号:897-091-629
更新日:2010年2月1日
平成2年(1990年)7月に策定した「練馬区長期総合計画」では21世紀に向けた新しい課題として(1)高齢社会とその対応、(2)余暇型社会とその対応、(3)高度情報社会とその対応、(4)国際化社会とその対応、の4つを掲げ、対処してきました。
21世紀の開幕を迎え、以下の(1)~(7)が新しい潮流としてそれぞれ関連しあいながら、地域社会に大きな影響を与えています。この長期総合計画を策定するにあたっては、こうした潮流が計画全体を貫く横断的な要素であることから、政策的な課題として総合的に対策を講じていくこととしました。
今後の練馬区の発展のためには、地域のみならず我が国の社会経済全体の構造的変化、とりわけ人口構造の急激な変化、情報通信技術の革新、有限な資源や環境への配慮等、技術の進歩や状況の変化に応じて、これまでの仕組みや慣行を見直し、新しい社会を築いていくことが求められています。
(1)少子・高齢社会
我が国の人口構造の高齢化は極めて急速に進んでおり、世界に例を見ない高齢社会が到来するものと見込まれています。21世紀の半ばには、日本の総人口は約2割減少し、3人に1人が65歳以上となると予測されています。
練馬区においても、人口の高齢化が一層進み、平成22年(2010年)には65歳以上の高齢者が5人に1人になると推計されています。一方、子どもの数も減少が見込まれており、超高齢社会が訪れます。
高齢化の進展の速度に比べて国民の意識変化や社会のシステムの対応は遅れています。長寿を喜び、高齢者はもとより、すべての区民が安心して暮らすことができる地域社会づくりが重要な課題です。そのためには、雇用や年金といった国が対応すべき事項をはじめ、医療、福祉、教育、生活環境等社会のシステムを高齢社会にふさわしいものとしていく必要があります。区はもとより、企業を含めて地域社会、家庭および個人が相互に協力・連携・協働しながら、それぞれの役割を積極的に果たしていくことが重要です。
また、「高齢者は弱者である」という画一的な見方ではなく、高齢者が長寿を喜べる社会を担い支える一員として活躍できるように、社会の仕組みを変えていくことも必要になっています。今後、区には、高齢者がその知識や経験を活かしながら生き生きと暮らし、医療や介護が安心して受けられる仕組みづくりが求められています。
高齢社会は一方では、少子社会でもあります。出生率が年々低下しており、地域社会の活力の低下が懸念されています。
この少子化の急激な進行を踏まえ、子どもを生み育てることに夢を持てる社会づくりをしていくことが急務です。
今後区は、国や東京都と連携して、少子化傾向に歯止めをかけるために、男女がお互いにそれぞれの多様な働き方や生き方を認め合える環境づくりや保育サービスの整備、充実を図るなど、地域社会全体で子育てへの支援に取り組む必要があります。
(2)環境との共生
温暖化や酸性雨等地球規模の環境問題が深刻さを増しており、これまでのような経済活動やライフスタイルの見直しが迫られています。身近な地域から地球全体にまで視野を拡げ、人類はかけがえのない地球に生きる共同体の一員であるという考え方も重視されつつあります。
地球環境を守るためには、これまでの大量生産・大量消費・大量廃棄という経済社会のあり方を根本的に見直し、廃棄物の発生抑制、再使用、再生利用を進めるなど自然環境への負荷の少ない循環型社会を形成していくことが極めて重要です。
ゴミ・ゼロ社会の実現を目指すとともに、地球温暖化防止京都会議(※注釈)〔平成9年(1997年)〕で決められたわが国の温室効果ガス削減目標(1990年を基準に2008~2012年の間に6%削減)の達成に向け、練馬区においても省エネルギーなどの取組を進め貢献していく必要があります。
また、平成12年(2000年)4月から清掃事業は東京都から移管され、一般廃棄物の処理が住民ニーズに基づいて一層きめ細かく対応できるようになりました。
さらに、身近な環境に「みどり」は貴重な役割を果たし、樹林地の保全や公園緑地の整備を進めることが強く求められています。今後区には、リサイクル、省エネルギー、緑化等環境との共生に配慮したまちづくりを推進していくことが求められています。
用語解説
※注釈:地球温暖化防止京都会議
大気中に排出される二酸化炭素等の温室効果ガスが気温の上昇をもたらし、様々な問題を引き起こすことが懸念されている。そこで、平成9年(1997年)の地球温暖化防止京都会議[気候変動に関する国際連合枠組条約第3回締結国会議(COP3)]では、二酸化炭素等の排出量の削減目標が国ごとに定められた。
(3)地域社会と人間形成
近年子どもをめぐっては、いじめ、不登校、学級の荒れ、凶悪犯罪などが大きな社会問題化しています。21世紀の日本と世界を担う子どもたちを、基礎的な学力を確保しつつ、個性・創造性豊かにたくましく育てていかなければなりません。そのためには、子どもたちの健やかな人間形成をめざして、家庭と学校と地域社会とが、それぞれの役割を果たすことが重要です。
命を大切にし他人を思いやる心、人間の尊厳を大切にする心が、家庭、学校、職場、地域社会において自然にまた広く、深く根付いていくようにする取組が必要です。
経済的効率を優先する傾向のあった社会は、より人間性を重視する社会に変化しつつあります。人々の価値観も経済的な豊かさばかりでなく、精神的な豊かさを求めるようになってきています。そうした社会の変化の中で、地域においては、人々のふれあいがあり、支え合いがあってこそ、人間らしい生活ができるのだという考え方、行政に任せきるのではなく、「自分たち」でつくろうという考え方が再認識されつつあります。
また、こうした動向と合わせてだれもが年齢を問わず、地域社会の中で、生涯を通じて学び、人間的に成長していきたいという欲求も一層高まりつつあります。今後区には、区民一人ひとりが個性を育み、自己実現できるための環境づくりが求められています。
さらに、性別、年齢、国籍、障害の有無等にかかわらず、だれもが差別されることなく、人間として尊重され、その個性や能力を十分に発揮できる社会を構築することは、人類の普遍の願いです。そのためにも、多様な個性や価値観をお互いに認め合うことが前提となります。男女にかかわりなく、喜びと責任を分かちあえる男女共同参画社会もこの考え方を具体化したものの一つです。今後区には、相互に認め合い、支え合える仕組みづくりが求められています。
(4)安全と安心
阪神・淡路大震災を契機に、災害に強い安全なまちづくりへの取組が改めて強く要請されています。また、犯罪や交通事故等に対する不安や危険をなくし、区民が安心して暮らせる生活環境づくりが課題となっています。
さらに、高齢者や障害者をはじめ、だれもが地域の中で支えられて、安心して暮らせることも重要です。平成12年(2000年)5月には、いわゆる「交通バリアフリー法」が成立しました。この法律には、高齢者や障害者にやさしいまちにするため、鉄道事業者と行政の役割が定められています。高齢者や障害者にやさしいまちは、だれにでもやさしいまちでもあります。「歩いて暮らせるまちづくり」の推進とともに、だれもが安心して暮らせる環境整備が必要です。
今後、区には、都市基盤を整備するとともに、地域の中で区民が協力し合える人間関係を築くことができるように援助していくことが求められています。
(5)分権・自治・協働
平成12年(2000年)4月に実現した特別区制度改革により、練馬区は名実ともに、基礎的な地方公共団体となりました。昭和27年(1952年)の地方自治法の改正によって、東京都の内部的団体とされて以来、半世紀に及ぶ自治権拡充運動の成果を勝ち取ることができました。
また、同じく平成12年4月に施行されたいわゆる「地方分権一括法」により、国と地方公共団体の関係は、従来の上下・主従の関係から対等・協力の関係へと変わりました。知事や区市町村長を国の下請け機関とする機関委任事務は廃止され、地域のことは地域が主体的に解決していく仕組みが強化されました。今後、地方分権のさらなる推進により、地域社会の自己決定、自己責任を果たしていくことが求められています。
そのためには、行政の効率性、透明性をより高めるなど行政改革への継続的な取組が重要です。その一つとして、区の施策や事務事業について、その効果を適正に評価するための制度を導入し、区民への説明責任を果たしていくことが必要です。
また、阪神・淡路大震災の際のボランティア活動の高まりを契機として、自発的に地域の課題に取り組もうとする住民活動がさらに活発になりつつあります。平成10年(1998年)3月には非営利の住民活動を支援する特定非営利活動促進法(NPO法(※注釈))が制定されました。今後区には、区民と区、区民相互が連携、協働して課題を解決していけるような仕組みづくりが求められています。
用語解説
※注釈:NPO
福祉、環境、まちづくり等で活動する民間の非営利団体全般をNPOといい、そのうち、法の定める分野の非営利活動を行う団体に法人人格を与え、市民活動の健全な発展を増進し、公益を図ることなどを目的とした法律がNPO法。
(6)経済再生
昭和から平成への転換期(1980年代後半から1990年代前半)にかけてのバブル経済の崩壊後、公共投資を中心とする大型経済対策がとられたにもかかわらず、日本の経済は低迷を脱していません。今後もかつてのような高度経済成長は見込まれず、むしろ安定した成長が望まれています。
一方、金融の国際化や各種の規制緩和が進み、経済構造の転換の大きな波が押し寄せています。21世紀を迎え、経済基盤を確固たるものとするため官主導から民需主導への産業振興策が急務となっています。
経済の活性化のためには、環境関連の研究・技術開発や情報技術の導入等による産業の高度化、消費者ニーズに適合した商品づくりやサービスの提供等が重要な鍵となります。今後区には、これらの変化を踏まえた産業の着実な振興を図るとともに、区内産業の後継者や創業を志す人の育成等が求められています。
また、PFI(※注釈)等の民間活力の活用のあり方の検討も必要になっています。
用語解説
※注釈:PFI
公共事業に民間企業の資金、ノウハウを導入することにより、国や地方自治体の財源負担の軽減を図るとともに、民間の活性化を促す事業手法。
(7)情報技術(IT)の進展
世界規模で進行している高度な情報技術の活用による産業・社会構造の変革、いわゆる「IT革命」は、21世紀繁栄の鍵といわれています。過去の蒸気機関、電力、自動車等に匹敵するほどの大きな技術革新の波ともいわれています。
とりわけ1990年代後半からの我が国におけるインターネットや携帯電話の爆発的普及は、社会生活そのものを大きく、しかも短期間に変えつつあります。あらゆる分野において、地理的、時間的な制約を越えて、新しい価値が創造され人間関係が築かれつつあります。
一方では、プライバシー侵害の危険性や「コンピュータウイルス(※注釈)」等情報技術の負の側面も指摘されています。
今後、国や東京都の電子化に向けた取組を踏まえ、こうした技術の進歩を区政や区民生活の中に生かしていくことが必要です。
また、個人情報保護等の安全対策にも取り組む必要があります。
用語解説
※注釈:コンピュータウィルス
ハッカーによりコンピュータに仕掛けられる伝染する性質を持つプログラムのこと。
お問い合わせ
企画部 企画課
組織詳細へ
電話:03-3993-1111(代表)
この担当課にメールを送る(新しいウィンドウを開きます)![]()
このページを見ている人はこんなページも見ています
法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202